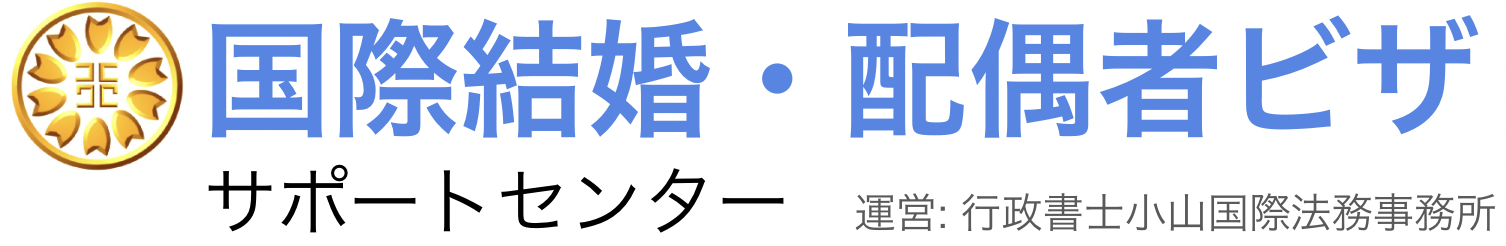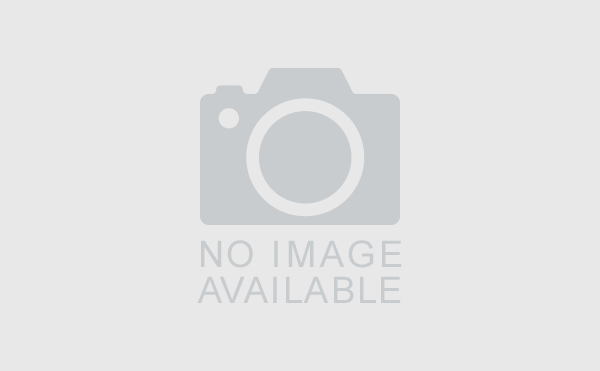日本で国際結婚した場合の国籍はどうなる?
目次
国際結婚後の国籍はどうなる?
国際結婚をしても、婚姻の手続きだけで国籍が変わることはありません。
国籍は各国の法律で決まる別の制度で、パスポートや戸籍の扱い、在留資格(ビザ)の取得とは役割が異なります。日本で暮らすための在留資格は「日本人の配偶者等」などの枠組みで扱われ、国籍の変更や取得とは切り分けて考えます。

結婚しても国籍は自動で変わらない
日本人と結婚しても、配偶者が自動的に日本国籍になることはありません。
日本国籍を希望する場合は「帰化」という別の手続きが必要です。一方で、日本人が相手国の国籍に変わることは通常はありません。
いずれも“別申請”が基本となります。
相手と同じ国籍を取る場合は?
自分が配偶者と同じ国籍を取りたいときは、相手国での帰化の要件を確認し、申請します。多くの国で、一定の居住年数、言語能力、素行・納税状況などが審査対象になります。
日本国籍をお持ちの方が自分の意思で外国籍を新たに取得すると、日本の国籍法上は日本国籍の喪失に関わる扱いになります。将来の生活(就労、社会保障、相続、兵役義務の有無など)への影響も国ごとに異なるため、相手国と日本の制度を確認して進めるのが安心です。
相手が日本の国籍を取る場合は?
外国籍の配偶者が日本国籍を希望する場合は、法務局での帰化申請が必要です。婚姻の実体(同居や生計の状況)、素行、在日年数などが総合的に審査されます。
日本で生活を始める段階では、まず在留資格(「日本人の配偶者等」)の手続きと取得が一般的です。帰化は中長期の選択肢として検討し、認められた後は日本国籍に基づきパスポートや戸籍、氏名表記などが日本の法律に則って管理されます。
二重国籍はできる?
日本では、原則として二重国籍は認められていません。
ただし、出生や親の国籍、海外での出生などの事情により、結果として複数の国籍を持って生まれるケースはあります。このような場合でも、日本では将来どこかの時点で国籍を一つに定めることが求められます。実務では、パスポート・戸籍・在留資格(ビザ)の情報が一致しているかが重要になります。

日本の二重国籍の原則と例外
日本の国籍法は重国籍の解消(単一国籍化)を基本方針としています。
典型的な例外は次のとおりです。
- 出生等による重国籍:父母の一方が日本人で、もう一方の国の血統主義や出生地主義が重なると、子が複数国籍を持つことがあります。
- 国籍喪失の猶予・困難:相手国の制度上、すぐに外国籍を変えられない・認められない場合があります。
いずれの場合も、「どうやって単一国籍にまとめられるか」が日本側の大原則です。
複数パスポートの併用や氏名表記の不一致は、旅券・出入国・身分関係で不都合を生むことがあります。
20歳/22歳の国籍選択ルール
複数の国籍を持っている人は、年齢に応じて“国籍の選択”が必要です。
- 20歳未満で重国籍になった人:22歳になるまでに、どの国籍を選ぶかを日本に届け出す必要があります。
- 20歳以上で新たに重国籍になった人:重国籍になった日から2年以内に国籍を選択します。
日本国籍を選ぶ方法は主に2つです。
- 日本国籍の選択宣言(日本の国籍を選ぶ旨を届け出る)
- 外国籍の喪失の手続き(相手国の手続きで外国籍をやめ、その証明をもって日本側に示す)
どちらを選ぶかは、相手国の法律を確認しながら総合して判断します。なお、日本国籍を変更する選択も制度上は可能ですが、日本での身分関係・在留資格・社会保障への影響が大きいため慎重な判断が求められます。
子どもの国籍はどうなる?
国際結婚で生まれた子どもの国籍は、出生時の条件や両親の国籍、出生地の法律などによって決まります。結婚しただけで自動的に両方の国籍が与えられるわけではなく、各国の制度の違いを理解しておくことが大切です。
日本では「血統主義」が採用されており、父または母のいずれかが日本国籍であれば、子どもは日本国籍を取得できます。
一方、出生地の法律によっては「出生地主義」が適用され、生まれた国の国籍が与えられる場合もあります。このように複数の国籍が与えられるケースは珍しくなく、結果的に子どもが二重国籍となることもあります。
日本国籍を取得する場合、出生後の手続きが重要です。主な流れは次のとおりです:
- 出生届の提出:日本国内で生まれた場合は14日以内、海外で生まれた場合は3か月以内に日本の役所や在外公館へ提出します。
- 国籍留保の手続き(海外出生の場合):一定の条件下では、国籍を維持するための「国籍留保届」が必要です。これを怠ると、日本国籍を失う可能性があります。

離婚してしまった場合の国籍はどうなる?
国際結婚後に離婚した場合でも、国籍そのものが直ちに変わることはありません。
国籍は婚姻の有無だけで自動的に喪失・取得するものではなく、結婚とは異なる独立した制度として扱われます。したがって、離婚しても日本人が外国籍を失うことはなく、外国籍の配偶者も自国の国籍をそのまま保持します。
ただし、注意が必要なのは在留資格(ビザ)との関係です。外国籍の配偶者が「日本人の配偶者等」という在留資格で日本に滞在している場合、離婚によってその資格を満たす条件がなくなるため、一定期間内に在留資格の変更や更新が必要になります。
また、帰化手続きの審査中に離婚した場合は、審査が中止されたり、条件を満たさなくなる可能性があります。帰化の前提として「日本人との安定した婚姻関係」が重視されるため、審査段階では特に慎重な確認が行われます。
子どもがいる場合も、離婚によって子どもの国籍が変わることはありません。 ただし、親権者や居住地が変わる場合、パスポートの申請や更新、在留資格の取り扱いなどで追加の手続きが必要になることがあります。
離婚が見込まれる場合や離婚後も日本での生活を希望する場合は、早めに手続きや今後の選択肢を確認しておくことが大切です。

戸籍・パスポートはどうなる?
国際結婚をすると、戸籍やパスポートといった公的な身分証明の内容が変わります。
これらは国籍の取得・喪失とは別の手続きが必要であり、婚姻や帰化などの状況に応じて対応が異なります。特に氏名の表記や国籍に関する記載は、日常生活や渡航、各種手続きに大きく関わるため、あらかじめ把握しておくことが大切です。

戸籍の実務(改姓・別姓の扱いと手続き)
日本人同士の結婚と異なり、国際結婚では姓(氏)の扱いにいくつかの選択肢があります。
日本人が外国人と結婚する場合、日本の法律では婚姻によって自動的に姓は変わらず、戸籍上は結婚前の氏名のままになります。
相手の姓を名乗りたい場合は、婚姻後6か月以内に「氏の変更届」を家庭裁判所に提出することで改姓が可能です。一般的には国際結婚の婚姻届を提出した市区町村役場での氏の変更届が可能となっています。
一方で、相手が日本に帰化した場合は、日本人同士の婚姻と同様に、戸籍上で同じ姓を名乗るか旧姓を維持するかを選ぶことができます。いずれの場合も、婚姻や国籍の変更に伴って戸籍の記載内容が変わる可能性があるため、住民票やマイナンバーカードなど他の公的書類も併せて更新する必要があります。
パスポートの氏名・国籍変更について
国際結婚や帰化によって姓や国籍に変更があった場合、パスポートの記載も更新が必要です。日本のパスポートは戸籍上の氏名・国籍と一致している必要があるため、変更後は早めに手続きを行いましょう。
主な手続きの流れは次のとおりです。
- 氏名が変わった場合:戸籍上の氏名変更後、パスポートセンターで新しい氏名への切り替え申請を行います。
- 国籍が変わった場合:日本国籍を失った場合は日本のパスポートは失効し、新たな国籍に基づいたパスポートの取得が必要になります。帰化により日本国籍を取得した場合は、日本のパスポートを新たに申請します。
申請の際には、戸籍謄本や帰化許可通知書、婚姻証明書などの書類が求められることがあります。また、パスポートの記載と航空券やビザの氏名が一致していないと渡航時にトラブルになる可能性があるため、氏名変更後は早めの手続きと確認が重要です。
国籍・配偶者ビザのご相談は【行政書士小山国際法務事務所】へ
国際結婚後の国籍や二重国籍、配偶者ビザの取得などは、手続きが複雑で専門的な知識が必要になる場面が多くあります。特に、国籍の選択や帰化申請、在留資格の変更は、申請内容や提出書類の不備によって時間がかかったり、認められないケースも少なくありません。
【行政書士小山国際法務事務所】では、これまで多くの国際結婚に関するご相談を受けてきた経験をもとに、お一人おひとりの状況に合わせたサポートを行っています。国籍の手続きやビザの申請について、疑問や不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

ご予約方法(WEBフォーム/電話)
ご相談は、予約ボタンから簡単にご予約いただけます。